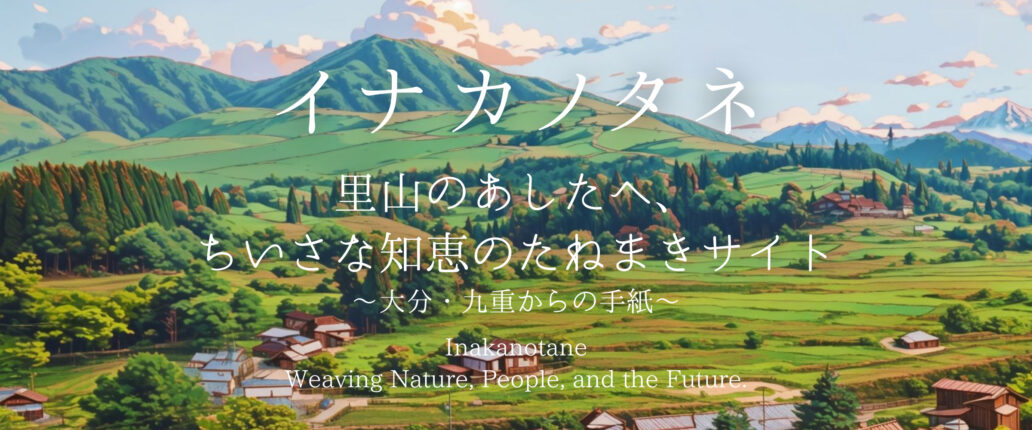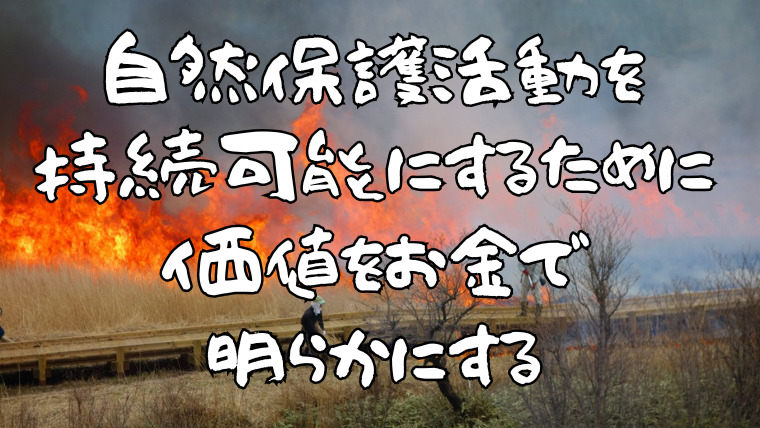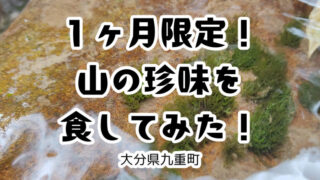「こんな活動、 一銭にもなりゃしないよ。」
里山や自然保護活動で よく聞こえてくるコトバです。

お金の話をします。
でも、それは冷たい計算ではなく、
僕から九重へのラブレターです。
「お金が目的じゃない!」
という人もいるでしょう。
でもきっと
お金が集まるということは、
実際に現場で体を動かすことが
できない人たちからの
応援のギフトと考えたら
うれしくないですか?
この記事では
大分県九重町で17年間
自然保護活動に携わってきた僕と
仲間たちが
お金というラブレターを通して
自然保護活動の価値を
たくさんの人たちに伝えることで
活動を地域の誇りや取り組みに
変えることができたかを
お話したいと思います。
なぜ自然保護活動の価値をお金で明らかにする必要があるのか
「一銭にもならない」という現場の嘆きを「誇り」に変えるために
人口減少の現代。
たくさんのボランティア活動によって、
地域の里山や自然が守られています。

でも本当にその価値を
明らかにしているところは少ないです。
「この地域は
本当に自然が美しいところですね」
と言われても
それが自然保護活動をしている人たちへの
直接的な応援にはつながりません。
ましてや地元に暮らしている人たちにとっては
あたり前の風景すぎて。
逆にその価値が認められて観光利用が進み
山・川・海が荒れれば荒れるほど
「あいつらフリーライドだ!」
「自分達はいったい
何のために活動しているのだろう?」と
疑問が生じてきます。
「なんでもかんでもお金じゃない。
自然保護の理想のもとにやってるんだ。」という
人たちに僕は頭が上がりません。
大分県九重町でも毎週のように
福岡・大分・熊本から
自分の時間とお金を使って
泥だらけになって
そして「楽しかった、ありがとう」と言って
帰っていかれるボランティアの方が
たくさんいらっしゃいます。
その素晴らしい活動を
孫子の代まで続けるには
どうしたらよいか。
そんな壁にぶち当たっています。
人口減少の時代。
今の日本は
高度経済成長のときの日本とは
ちがう時代に入りました。
少子高齢化、インフレ、物価高の悪循環で
ますます生活はきびしくなっています。
ボランティアの皆さんの高齢化も
進んでいます。
独身時代、毎週金曜日の夕方
「お前はこれからどうするんだ?」と言って
賞味期限の切れた
あったかいラーメンを食べさせてくれた
やさしいあの人。
いつも笑顔で
泥がついたままの大根やカブを
山のように分けてくれたあの人。

口数は少ないけど誰よりも
九重の植物に詳しくて
少年のようないたずらな目で
いろんな実を食べさせてくれた
あの人。
みんな遺言のように
「九重を頼むぞ」といって
去っていかれました。
その度に、この自然を
どうつないだら良いのだろうと
悩みました。
人や社会がどんなふうになったって
自分の体がいつか
この世から亡くなったって
大事なものは
ずっとここで残っていてほしい。
きっとみんなそれを願っているはずです。

資本主義の中で、里山の持続可能性を守るという「誠実な選択」
現代社会では
僕たちの暮らしも自然保護活動も
「お金」の問題から
のがれることができません。
ましてや自然保護のためのお金は
公的な税金だったり
みんなの思いが集まった
寄付金が利用されます。
ということはお金を出して
応援してくれる人たちのためにも
僕たちや地域の人たちの活動の価値を
客観的にお金であらわす必要が
あるんじゃないかと思ったんです。
そしてその基準は
誰がみても
「うん!そうだね」と
納得できるものだといいですよね。
自然の価値を測るCVM(仮想的市場評価法)とその限界
観光客の「支払意思額」だけでは現場の心は動かない
よくあるのが、
自然を守るために
いくら払っても良いか人々にたずねて
その結果をもとに
自然の価値を評価する方法です。
これを難しい言葉でいうと
CVM(仮想的市場評価法)と言います。

これは
確かに今までなかった自然の価値をはかるのに
わかりやすいものです。
この方法を利用して国立公園の自然の価値を
明らかにしようとした実験が
我らが阿蘇くじゅう国立公園阿蘇エリアにて
おこなわれました!↓↓
「国立公園阿蘇地域における来訪者の観光行動と環境保全への支払意思額の関係」
でもこの結果を見ていて
もやもやしてしまったのは
「現場で汗をかいている人たち」ではなく
「他者」が基準であることです。
観光客の支払意思額は「806円」と聞いても
「おおありがたい!」なのか
「う〜ん806円だけ?」と思うのか。
この方法はどちらかというと
寄付を募りたい人が
どういった層に
どのくらいの金額を
どこで求めることができるかという
寄付募集の基準になると思います。
「他者の評価」よりも自分たちの「流した汗」に光を当てる
でもこれでは
その自然を利用し楽しんでいる
観光客の人たちや行政の皆さん、
そして地元の人たちには
自然の価値が
全く伝わりません。
「ふ〜ん、そうか。
みんな806円払いたいんだ。
高いの?安いの?
よくわからない。」
と思うだけでしょう。
目の前の自然がいったい
どのくらい素晴らしいのか
感動という実体験だけではなく、
現場の汗に光を当てて
数字で表すことができたら
もっと伝えられるのかもしれない。
そう思ったんです。

では現場で作業している人たちを
勇気づけたり
本当に活動に必要な資金を
行政や支援者から引き出すために
どんなふうに
価値を数字で
あらわしたらよいでしょうか?
【実践】ボランティア活動費を「公共工事設計単価」で積算する〜大分県九重町のくじゅう連山の事例〜
行政との協働を加速させる「共通言語」としての積算シミュレーション
そこで僕たちは
環境省と協力をして
実際に大分県九重町、竹田市で行われている
野焼き活動や登山道整備活動など
現場で汗をかいている人たちの
ボランティア活動を基準に
都道府県の公共工事設計単価を
利用して積算しました。
例
普通作業員の単価を利用、時間と人数をかけて人日として算出
例:普通作業員単価:19,000円/日(8時間)
作業にかかった時間が2時間、人数が10人なら
0.25時間×10人=2.5人日
19,000円×2.5人日=47,500円
すると僕の地域での自然保護活動。
実は毎年2,000万円以上の費用が
かかっていることがわかりました!!
に、にせんまんえんっ!!!
皆さんの九重への
愛の総量は思った以上でした!!!

年間2,000万円の価値。数字で見えてきた「愛の総量」
これを見て活気づいたのは
「お金で動いているんじゃない!」という
なんと現場のボランティアの人たちでした。

「自分達がやってきたのは、
こんなに価値があったんだ!」
その気づきが 明日のボランティア活動の活力に。
環境省も大分県九重町も竹田市も
この結果を見てびっくり。
全部この作業が委託になったら、
行政がお金を出して守ることなんて
とうていできない。
みんなそう思ったはずです。
苦情やクレームではなく、数字を添えた「提案」で未来を作る
だから行政も民間もみんなで
このボランティア活動が
僕たちの代が終わった後も
子どもの代も孫の代も
ずっと続いていくように
ボランティア活動に対する
お金や人の支援を
しっかりやっていこうということに
なりました。
お金は「ラブレター」。行政や支援者の心を動かす伝え方
寄付金付きツアーやエコツーリズムへの展開:利用と保護の両立
僕たちの地域では
この結果をうけて
志の高いガイドの方、ホテルの方、企業の方と
協力をして
利用と保護が同時に進むような
エコツーリズムや寄付金付きツアーなどの
販売を始めました。
くじゅうネイチャーガイドクラブさんでは
タデ原のガイドを
全て協力金(寄付金)付きツアーとして
旅行会社さんに
販売してくれています。
またガイド料で集めたお金を利用して
みんなで体を動かしながらくじゅうの自然を守る
サポートスタッフ制度を創設。
法華院温泉山荘さんと協力して
その活動を充実させています。
九重星生ホテルでは、全プランを
協力金(寄付金)付きプランとして
販売してくれています。
(料理もとってもおいしい!温泉も素晴らしい!)
九電産業株式会社さんは、
リフラッシュウォーターという
スポーツ飲料を販売していますが、
そのうち九重ラベルのものは全て
協力金付き飲料として
販売してくださっています。
小松地獄は令和2年7月豪雨で大きな被害を
受けましたが、令和7年7月に復活。
筋湯温泉観光協会が
管理していくにあたり、
入り口には環境保全金の募金箱が
設置されてました。
地獄で卵をゆでて、
大分県九重町の日本一の
地熱パワーを感じてください!

毎年9月におこなわれている
やまなみ感謝祭
(九重・飯田高原観光協会主催)では
くじゅうの自然を守るための
協力金付き手ぬぐいを
販売してくれているほか
会場内で募金を集めて
寄付してくれています。
それだけでなく、
賛同してくれた九重町・竹田市の
ホテルや旅館、飲食店には
くじゅうの自然を守る募金箱を
設置してくれています。
あなたの地域の自然保護活動も、きっと誰かへのラブレターになる
自然保護活動の価値は
見えにくいけれども
みんなの共通言語である
「お金」を通して見つめると
広くその価値を伝えることができるし、
活動の輪もきっと広がっていきます。
始めは点であっても
いくつかが線となり
それがいつか面になって
いくのでしょう。
まだ僕たちのエリアでも
取り組みは始まったばかりです。
大きな活動は誰か一人の勇気から。
長者原ビジターセンターでも
ボランティア団体と行政の間に入って
地域の自然保護のためのファンド作りや
自然保護活動の支援を行なっています。
(活動報告書のダウンロードができます!)
「数字」は一見、冷たくて
ボランティア精神や自然への思いを
否定するようなものに
見えるかもしれません。
保護活動のための
数字を実際に積み上げる作業は、
正直しんどいこともあります。
でも、その数字の向こう側に、
守りたい景色や仲間の笑顔がある。
僕にとって数字は
九重へのラブレターなんです。
僕が今、
こうして数字と向き合っているのは
賞味期限が切れたラーメンを食べながら
将来を案じてくれた人たちへの
『お節介なほどの愛』への
僕なりの返信でもあります。
「数字」はあなたの思いを
ラブレターに書き換えてくれて
たくさんの人たちの心に届けてくれます。
ぜひ地域みんなでやっていることを
「数字」というラブレターに
変換してみませんか?
価値を数字で見せることは、
あくまでスタートラインです。
そこから実際に行政や大学を巻き込んで、
どうやって現場を動かしていくのか。
僕が17年かけて泥臭くあがいて見つけた
『具体的な突破術』については、
こちらの記事にまとめました↓↓

観光と自然保護の未来を作りたい。
そんな気持ちでこの記事を書いています。
こちらもぜひ読んでください!↓↓


僕たちが活動している
大分県九重町で
ぜひ一緒に活動してみたい!という方
ぜひXからコメントやDMください!