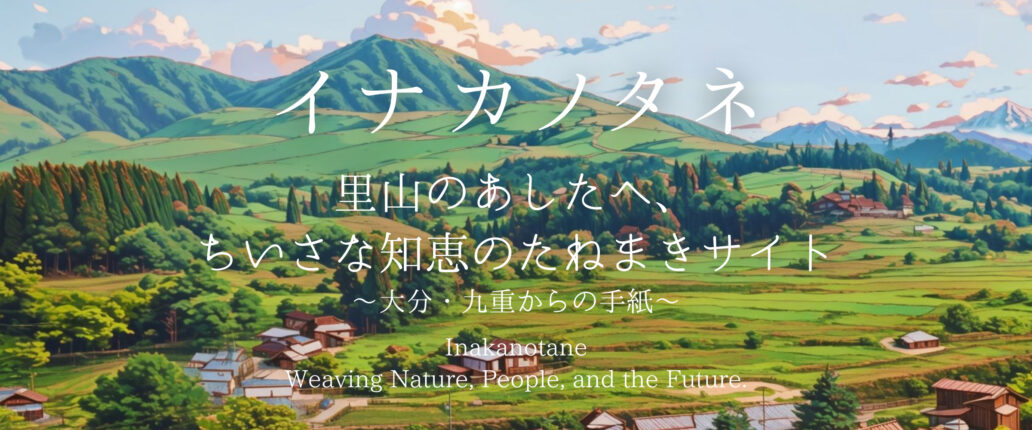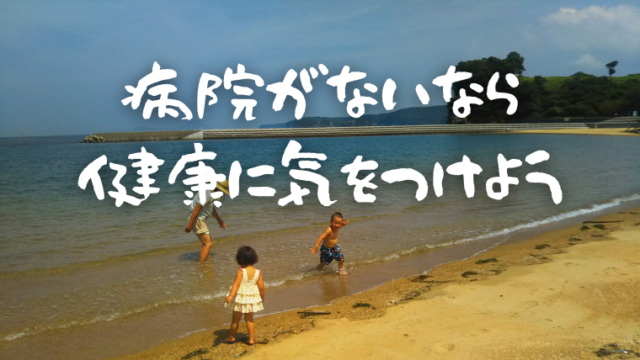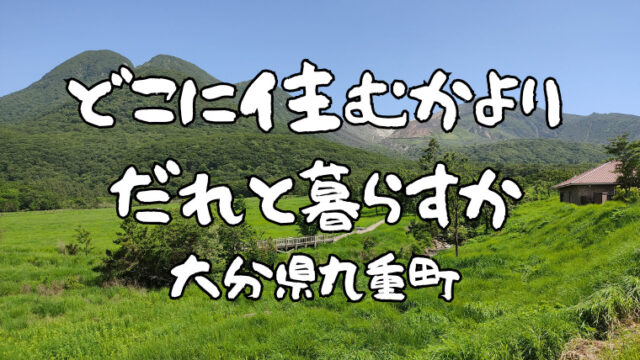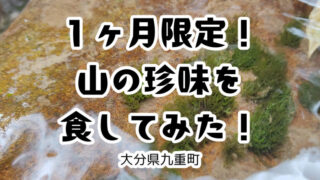「え、こんな田舎の道の駅でもお米が高くなったの!!?」
となり町の道の駅をのぞくと、
かつて見たこともない驚きの高い価格でお米が売ってました
(悪いことしてないのにドキドキする)

私は小さな小さな自給的な米農家ですが
このお米の価格の高とうに
いくらなんでも… という気持ちと
やっと近所の農家さんたちがむくわれる…
(山間部での米の生産はみんなとても大変)
という気持ちと半々。
ただしあまりに急な米の値段の上がり方には疑問。
流通の構造的な問題をうきぼりにしたように感じます。
さてさて、この米不足・米価格の高とうは
いつまで続くんでしょうか?
今回は「米が高いから自給自足ノススメ」というテーマで
お話させていただきます。
お米はいつか安くなるのか?
お米がどのスーパーに行っても手に入らない。
でもアメリカから輸入米が入ってきたら?
アジアからもっと安い米が入ってきたら?
確かに今みたいな米不足は解消されて
「お米」は一気に安くなるでしょう。
でも私は日本国内でつくられた
「国産米」はこれからも高騰し続けるのではと考えています。
なぜならば、
政府には国産米の輸出量を
5年後の2030年には
現状の7倍以上に増やす基本計画があります。
そしてもう一つ重大なことは、
稲作農家の高齢化が本当に進んでいるからです。
米農家の高齢化は深こく!
令和5年の農水省のデータによると65歳以上が全体の約7割を占めています。
稲作をおこなう法人経営体数は15年前に比べると200%以上増えてますが、
大規模経営体においても、約4割では後継者が確保されていないという現状です。
私が住んでいるところでも
(九州最高峰のくじゅう連山のふもとの山の中)
大規模に田んぼを引き受けて稲作を頑張っている若者もいますが
年々、田んぼを作っていた高齢者がいなくなり
目に見えるように
荒れはてた耕作放棄地が増えています。
田舎で自給自足にチャレンジしたい人にはチャンス到来!?
ということは
自給自足をしたい!と考えている人は
田舎に行けば土地がたくさんあるということです!
「安心安全な出どころのわかる食べものを作って食べたい!」
「お米が大好き!日本の里山も大好き!」
そんなあなたにはチャンスしかありません(笑)
自給自足に必要な田畑の大きさなどについては
過去ブログ↓↓をご覧ください!
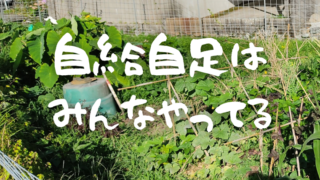
しかしお米だけ作っていても
食っていけるのかどうか不安だという方が
たくさんいらっしゃることと思います。
田んぼで暮らしが立っていくのか問題
私が住んでいるような山の中の田んぼは
「経営」という観点から
田んぼだけで暮らしを立てていくのはとても難しいと感じます。
なぜならば、平野部とちがって
山を切り崩して田んぼができているので
田んぼのあぜがとても大きく
かつ1枚あたりの田んぼが小さいからです。
大規模農業で生産する量にはとてもかないません。
また急斜面を流れる川からあちこち水路をひいているので
水路の草切りや石あげなど、
高齢化が進んだ田舎では維持管理がとても大変です。
田んぼで食っていけるか問題はグリーンツーリズムで突破!
でも田舎で田畑を作りながら
生計を立てている方はたくさんいらっしゃいます。
特に私のように新規参入して生計が立ちやすいと感じているのは
グリーンツーリズムです。
グリーンツーリズムとは、農業をしながら
レストランや民宿を複合的に経営するやり方です。
私の地域でも平野部には生産量で勝てないから
質で勝負だ!ということで
有機農業をしながら
農家民宿や農家レストランを軌道にのせて
頑張っている方もたくさんいらっしゃいます。
毎週大分市内のオーガニックマーケットに出店して
たくさんの固定ファンを生み出している方もいます。
わが家でも妻が小さな農家民宿を始めました。
一方で、どこかに勤めながら
食べる分程度の田畑を作る
一般的な兼業農家の方もたくさんいます。
田舎の仕事の給与は安いと言われますが、
兼業で食べ物を作っていれば
お金はそれほどたくさん出ていくことはありません。
また「食べものが家にある!」と思うことが安心感につながり
勤めながらでも
新しい事業にチャレンジできるのではと感じます。
(いわゆる副業起業ですね)
かくいう私自身も
自然保護の仕事をしたり観光振興の仕事をしたりと
いろんなチャレンジができるのは
食べものが家にある安心感からです。
人間は経済ではなく自然を食べて生きている
昨今のお米問題は、
お米だけでなく
私たちの毎日食べる食べものが
実は不安定な供給のもとで成り立っているということを
教えてくれました。
ウクライナ侵攻や中東情勢の不安定化など
輸入食料に頼りきっている
日本の食べ物を取り巻く環境は
日に日に厳しくなっているように感じます。
さらに全世界的な気候変動により
大型台風が何度も上陸したり、集中豪雨が毎年発生したり、
夏に35度以上の高温が続いたりと
作物が思うようにできない事態も生じてきています。
食べものの問題の根本には
人間は経済だけを食っているのではなく
「自然」を食べて生きていることにあるのではないでしょうか。
『日本の美しい自然を食べて毎日生き生きと暮らす。』
そんな生活が実現可能だとしたら、
チャレンジしてみたいと思いませんか?
大分県九重町ではそんな暮らし方ができます!


このブログはこんな思いで書いてます。


ぜひ九重町で一緒に活動したいという方がいれば
気軽にXからコメント、DMください!